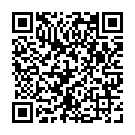令和3年度
6年 総合「尾崎の歴史」
5校時,6年生は小野寺憲雄さんを講師に迎え,尾崎の歴史について学びました。憲雄さんは長い間,本校4年生のワカメの養殖体験を支えてくださった方で,6年生も2年前にお世話になっています。


尾崎・片浜だけでなく気仙沼全体で盛んだったノリや牡蠣の養殖の始まりや衰退とワカメ養殖への移行などについてお話してくださいました。震災前に面瀬川の河口に広がっていた干潟は豊かで,戦後の食糧難の時もタマガイ(能なしツブ),ウバガイ,ホッキ貝などが支えてくれたこと,それを採るのが子どもたちの役目だったことなどをお聞きしました。


校長室でお聞きすると,尾崎の養殖で今,苦労しているのがホソジュズモという海藻で,筏にくっついて牡蠣やホタテの成長を阻害するとのことでした。(冬場はホンダワラ類がワカメの筏に付いてからまり,ワカメの成長点を痛めるのだそうです。)このホソジュズモ,実は海藻紙の材料になるとのこと。鉄腕ダ○シ○のように厄介者の有効利用ができるのではとワクワクしてきました。「6年生の誰か,個人研究の課題にしないかなぁ」
小野寺憲雄さん貴重なお話,有り難うございました。


尾崎・片浜だけでなく気仙沼全体で盛んだったノリや牡蠣の養殖の始まりや衰退とワカメ養殖への移行などについてお話してくださいました。震災前に面瀬川の河口に広がっていた干潟は豊かで,戦後の食糧難の時もタマガイ(能なしツブ),ウバガイ,ホッキ貝などが支えてくれたこと,それを採るのが子どもたちの役目だったことなどをお聞きしました。


校長室でお聞きすると,尾崎の養殖で今,苦労しているのがホソジュズモという海藻で,筏にくっついて牡蠣やホタテの成長を阻害するとのことでした。(冬場はホンダワラ類がワカメの筏に付いてからまり,ワカメの成長点を痛めるのだそうです。)このホソジュズモ,実は海藻紙の材料になるとのこと。鉄腕ダ○シ○のように厄介者の有効利用ができるのではとワクワクしてきました。「6年生の誰か,個人研究の課題にしないかなぁ」
小野寺憲雄さん貴重なお話,有り難うございました。
2
6
2
0
4
7
4
ブログ
面瀬小ニュース
記事がありません。
連絡先
宮城県気仙沼市松崎下赤田58番地
TEL 0226-22-7800
FAX 0226-24-7215
omose-sho◎kesennuma.ed.jp
(迷惑メール防止のため@マークを◎にしています)
学校周辺の地図
QRコード