

月立小学校の日常を紹介します
2023年6月の記事一覧
校内研究授業~高学年~
子供たちが、新しい事を知る楽しさを味わえる授業はどうあればよいか?を月立小学校の先生方で勉強する研修会がありました。
今回は、高学年の子供たちと担任の先生とで創る算数の授業参観しました。
月立小学校は複式指導での授業をしていますので、5年生、6年生とそれぞれの教科書の内容は違いますが、実は関連事項が多く、6年生は5年生の学習を振り返り、その振り返りを基にして、今の学習をしています。
この関連事項の重なりがある展開が、複式指導のよさであると考えています。



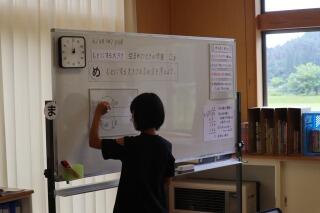






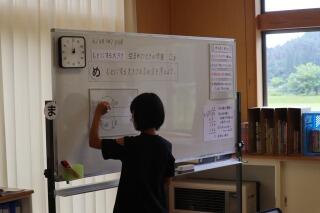



毎日の授業の中で、子供が「なるほど~」「あっ、わかった」「なんで?」「そういうことか」などなど、日常の言葉があふれる姿があればあるほど、子供たちの時間になります。そして、間違った時こそ、本当の学びの時間でもあります。
子供の楽しさが見える時間を、先生方と追い求めたいと思っています。
早稲谷鹿踊親子教室 開講式
昨夜、伝承館で開講式がありました。
4年生以上の子供たちが集まり、鹿踊親子教室での目標を話していました。
















早稲谷鹿踊が誕生した言い伝えには、心打たれる思いがあり、伝統芸能として受け継ぐ部分も大事ですが、その思いに触れることで、より深い継承になるのだろうと感じていました。






早稲谷鹿踊保存会の皆様方には、今年度もお世話になります。


どうぞよろしくお願いします。
野外活動 解団式
昨日、野外活動の解団式がありました。
「1週間前は野外活動だったんだよね」との、つぶやきもあり、あっという間に思い出になってしまったことを振り返っていました。
そんな中で、7人の子供たちからは、それぞれ心で感じてきたことを、今後の生活に生かして行きたいとの発表がありました。




ひとつひとつの活動を終える度に、成長を感じる子供たちでした。
プール開き
今日の朝会はプール開きです。
水泳の学習は、水に触れ、その感覚に親しむことと、水中での安全に関する知的な発達や水の事故を未然に防ぐ論理的な思考力を育むことを目的として学習をします。
大きな目的は「命を守る」学習ですね。












その目的の中で、子供たちは水に潜ったり、浮かんだり、泳ぎを覚える活動を通して、水泳の楽しさを味わいます。
そして、いざという瞬間に働くとっさの行動を身につけます。
そして、いざという瞬間に働くとっさの行動を身につけます。
水泳で頑張ることの発表した代表の子供たちも、水での活動や泳げるようになることを発表していました。
この3年間は子供たちの活動も小さくなっていましたが、プールでの水しぶきが青空に高く届くくらい、ひと夏を楽しく過ごせればと思います☼
遠足
今週は高学年の野外活動、低学年のまちたんけん、そして1~4年生の遠足と、社会とのつながりを広げ、深める学習の1週間でありました。
雨が心配されましたが…晴れを祈る小さなてるてる坊主が…リュックサックから空を眺めていました。
本当にうれしくて、うれしくてたまらない、気持ちで始まった遠足です。
本当にうれしくて、うれしくてたまらない、気持ちで始まった遠足です。

高学年に「行ってきます!」のあいさつをして出発です。
今週の野外活動の出発の集いを見ていた1~4年生だったので、自信をもってあいさつができました。




今週の野外活動の出発の集いを見ていた1~4年生だったので、自信をもってあいさつができました。




バスに乗り込んで、始まったのがカラオケ大会です。
コロナ禍で、声を出すのは控えましょう…から、いわゆる子供らしさを認めながら、子供らしい今を楽しんでいました。
本当に、いい時間です。

コロナ禍で、声を出すのは控えましょう…から、いわゆる子供らしさを認めながら、子供らしい今を楽しんでいました。
本当に、いい時間です。

岩井崎に到着して、大海原の景色を眺めました。
校歌にも「♪君鼻山にのぼり見る 太平洋の波の色♪~」とありますが、子供たちの目には、どんな色に見えたのでしょうか?校歌に出てくる景色を、実際に見る時間にもなります。



校歌にも「♪君鼻山にのぼり見る 太平洋の波の色♪~」とありますが、子供たちの目には、どんな色に見えたのでしょうか?校歌に出てくる景色を、実際に見る時間にもなります。



いよいよ、磯での活動です。波打ち際で海に素足を入れて「冷たい!」と声を弾ませ、貝殻を見つけては、その模様に見入ったり、岩井崎の潮吹き岩の「ドォーン」と言う音とともに高く吹き上がる吹いた潮の高さに「オーー」と驚いたりと、月立とは違った自然を感じていたようでした。












岩井崎での活動でふくらんだ「楽しさ」をリュックに詰めて、次は、モーランドです。
モーランドでは、ローラーすべり台や遊具、景色、お弁当、動物とのふれあい…と、帰りのリュックに詰め切れないほどの楽しさを満喫していました。


























特に、動物とのふれあいは、生き物の「あたたかさ」を実感する大切な時間になったと思います。
子供たちの心や感性にささやいてくる命の大切さや慈しみを感じてくれればと思っていました。






今週は、月立小学校の子供たちの心の成長につながる「恵み」がたくさんあった1週間であったように思います。そして、無事、終えることが出来たのも、おうちの方々の陰の支えがあって、今週の子供たちの笑顔につながったと思っております。






今週は、月立小学校の子供たちの心の成長につながる「恵み」がたくさんあった1週間であったように思います。そして、無事、終えることが出来たのも、おうちの方々の陰の支えがあって、今週の子供たちの笑顔につながったと思っております。
本当にありがとうございました。
野外活動⑫
おかえりなさい!
2泊3日を乗り越えた、7人のプレイヤーが帰ってきました。
到着のつどいでは、代表から、仲間との絆を深められた感想があり、これからの思い出とともに、これからの子供自身の支えになっていく心の結びつきが出来たものと感じました。




修学旅行や野外活動などの学校行事は、おうちの方々も経験している行事でもあるので、世代間を超えた思い出話が出来ます。その世代間の話の中で、おうちの方々から、大人になって行く歩み方を学ぶ機会にもなります。子供たちには、おうちの方々に話をしてね!と話していますが、その機会をうまく使って緩やかに伝えていただけたらと思っています。
2泊3日、本当に頑張ってきた5・6年生の子供たちに、みんなで拍手したいと思います。
お疲れ様でした。
野外活動⑪
いよいよ、野外活動も終わりに近づいています。
昼食を食べて、記念撮影!


月立小に向けて、出発!!
昼食を食べて、記念撮影!


月立小に向けて、出発!!
野外活動⑩
野外活動の最後のプログラムのウォークラリー!
絵地図を見ながら、チェックポイントを探し回って、ゴールを目指します。






みんなで力を合わせて、ゴールを目指しましょう!
野外活動⑨
3日目の朝を迎えました。
朝の集いに参加し、体操をして、気持ちと体にスイッチオン!ですね。








朝ご飯を食べて、今日もスタートです!
野外活動⑧
2泊3日の野外活動の中で、一番の盛り上がりを感じるのは…キャンプファイヤー!!
厳かに恵みの火を迎入れ、友情と協力を深め会うスタンツやフォークダンス、そして、その恵みの火の温かみと感謝の気持ちの中で、今までの「自分」と、これからの「自分」を見つめながら火を送り、本当によい時間が流れていました。




























それぞれの役割を果たしながらも、友達同士、先生と子供たちの絆が、ぐっと近づいた事を、肌で感じた時間でもありました。








キャンプファイヤーの後は、ゆっくりお風呂で疲れを流して、ロビーでのくつろぎの時間もありました。
くつろぎの時間の駄弁っている子供たちもすてきでした。
くつろぎの時間の駄弁っている子供たちもすてきでした。

今晩はゆっくり休んで、明日、少しだけたくましく、そして、しなやかさを身につけて元気に帰ってきてほしいと思っています。
本当に、頑張っている姿が見られた2日目の夜でした。
おやすみなさい☆彡
まちたんけん
1・2年生のまちたんけんです。
新月地区の商業施設で、社会勉強をしてきました。
子供たちの日常にある景色ですが、家族と出掛ける景色と、仲間と出掛ける景色では感じるものは違うものです。




















生活科の実体験が、3年生以降の勉強に関連付けられたり、少し深掘りした知識につながって行きます。とても意味あるまちたんけんでした。
野外活動⑦
「洋上めぐり」のスナップです。
船に乗り込み、志津川湾を巡って、海側から見る陸地の風景も貴重ですね。





みんな元気そうで、何よりです。
船に乗り込み、志津川湾を巡って、海側から見る陸地の風景も貴重ですね。





みんな元気そうで、何よりです。
野外活動⑥
焼き板作りの様子です。
板を焼いて、磨きを掛けて、そして絵付け。
思い出を形に残す作品となりました。







そして、ランチタイムです。

早いもので、野外活動も折り返しです。
残りのプログラムも、楽しんでほしいですね。
板を焼いて、磨きを掛けて、そして絵付け。
思い出を形に残す作品となりました。







そして、ランチタイムです。

早いもので、野外活動も折り返しです。
残りのプログラムも、楽しんでほしいですね。
野外活動⑤
野外活動の2日目が始まりました。
昨日の夕食の様子も含めて、元気に朝を迎えた様です。





朝食をしっかり食べて、今日も1日、楽しんでほしいと思います。


フレー フレー 月立っ子!
昨日の夕食の様子も含めて、元気に朝を迎えた様です。





朝食をしっかり食べて、今日も1日、楽しんでほしいと思います。


フレー フレー 月立っ子!
留守番
高学年が野外活動に行っている間の留守番は、1年生~4年生です。
3・4年は、朝の会でクイズをしている姿がありました。自分クイズを出して、みんなに当ててもらって楽しんでいました。


業間は、体力作りでマラソンをしました。3分間走で、3周~5周走っていました。夏空が気持ちよく感じました。一緒に走ってみると、競い合いたくなってしまいます。




その業間には、育てているミニトマトへの水やりをしていました。プランターの中の雑草を抜いて、目と手を動かし、気持ちも動かし、植物を大切に育てようとする心が見えた瞬間です。


高学年とは場所は違いますが、それぞれの場所と時間、そして、それぞれの子供自身の場所と時間の中で、それぞれの育ちを感じていた所です。
「一人一人のよさが大きくなっていけばいいなぁ…」と、応援していた所です。
野外活動④
今晩の夕食作りが始まりました。
もちろん定番の「カレー」です。



どんなカレーができあがるか、楽しみです。
野外活動③
楽しそうな便りが届きました!





見ての通り、楽しさ満喫!
気持ちいい✨
野外活動②
自然の家から、徒歩で海辺まで歩きます。いつもの山の景色から、潮騒を感じながら海の景色を眺めての場所移動です。


いかだ作りに取り組んでいます。うまく組めるか、みんなで協力します。





お昼は、持ってきたお弁当を食べています。活動した後のお弁当は…うまい♡!!




午後の活動も楽しみます。
野外活動①
志津川自然の家に到着しました。
みんな元気です☺






野外活動出発式
気持ちのよい青空に迎えられて、野外活動の出発式をしました。
私の方からは、お天気も含めて、様々な方々からの「恵み」を大切にして、2泊3日を過ごしてほしい願いを伝えました。そして、楽しんで来てほしいことも。




いつもお世話になっている高学年のみんなへのエールになればと、在校生にも立ち会ってもらいました。
おうちの方々、1年生~4年生までの子供たち、そして先生方という、みんなに見守られての出発式は、月立小学校の一体感を感じさせる時間になりました。
7人のプレイヤーが、それぞれの役割の中で、学校では味わえない楽しさを感じて、その楽しさを持ち帰ってきてほしいと思います。
おうちの方々も、お見送り、ありがとうございました✨
野外活動結団式
いよいよ、明日から5・6年生の野外活動です。そこで、気持ちを1つにする会「結団式」がありました。
引率の先生方3人からの心構え、もちろん、私からもエールを送りました。






そして、野外活動のプレイヤーである7人からも、頑張ることの発表がありました。


野外活動のテーマは「ONE for ALL,ALL for ONE(一人はみんなのために、みんなは一人のために)です。
もともとは、アレクサンドル・デュマ・ペールによる冒険活劇小説「三銃士」でダルタニャンたちが叫ぶ言葉です。映画「三銃士」でもクライマックスで心をひとつにする言葉で、あの場面に勇ましさを感じますね。まさに、これから野外活動に向かう、冒険が始まる場面にふさわしいテーマです。
7人のプレイヤーからは、「楽しい時間を」「友情を深め」「自然を感じる」「準備をしっかり」「まわりを見て」「友達と友情を」「自然を大切」などなど、これからの思いがあふれていました。
明日は、天気にも恵まれそうなので、おうちの方々の応援、先生方の支え等、いろいろな恵みを感じながら、元気に出発してほしいと思っています。
楽しんできてね✨
大豆のたねまき
今日はお天気が良く、3・4年生は畑に出かけ、大豆の種まきをしました。
10列の畝に種をまいて、周りに網をまわしました。
















栽培から収穫、そして加工という一連の工程を体験的に学ぶ意味は、その工程には「人」が存在し、育てるための苦労や工夫を知ることはもちろん、その人を支えている生き方に触れることに大きな意味があります。今回の種まきにも、こだま隊のカズ~HERO~隊員に教えていただきました。
いつもながら、本当にありがたい存在です。
カズ~HERO~隊員、ありがとうございました。
東北楽天イーグルス未来塾
今日も雨降りの1日でした。それも、強めの雨が1日中降り続きました。
そんな中、東北楽天ゴールデンイーグルスの元選手:岩崎達郎さんが来校しました。
子供たちに、これからの夢や目標などについて、考えるきっかけ作りを目的に各地で開催しているそうです。
岩崎選手は、2013年の楽天ゴールデンイーグルス優勝のスタメンメンバーであったそうで、田中投手(マー君)の話題もありました。


体育館で、ボールを使ったアクティブをした後に、岩崎選手の小学生の頃の夢から現在までの事の話をしていただきました。




いろいろな方々に支えてもらった事に対する「感謝」や、自分の長所を大事にして、伸ばすこと。そして、失敗しても、また挑戦する大切さを教えていただきました。







いろいろな方々に支えてもらった事に対する「感謝」や、自分の長所を大事にして、伸ばすこと。そして、失敗しても、また挑戦する大切さを教えていただきました。



「学」が付いている時期、小「学」校、中「学」校、高等「学」校、大「学」…は、とにかく挑戦と失敗を繰り返して、自分に力を蓄える時間です。だから失敗、間違ってもOKなのです。失敗から学んで行くことが大事です。
岩崎選手のメッセージの中の「失敗しても、また挑戦!」が、とても大事なメッセージとなりますね。
岩崎選手のメッセージの中の「失敗しても、また挑戦!」が、とても大事なメッセージとなりますね。
最後は、岩崎選手とみんなで記念撮影をしました。ユニホームもプレゼントしていただき、そのユニホームでの記念撮影もしました。




いろいろな人から話を聞くことって、良いものですね✨
岩崎選手に感謝です。ありがとうございました。
トランプ
今日も雨降りの1日でした。
教室で過ごす時間が多くなり、そこで始まったのが「♤♧トランプ♡♢」です。
低学年の教室に行くと、輪になって「銀行」をしていました。トランプやカルタといった遊びは、ルールがある遊びであるため、ルールを守ることによって楽しく遊べる事を学ぶ時間にもなりますね。オンラインゲームや携帯型ゲームのような遊びが仕組まれていないので、人との関わりの中での学びは多いですね。


1・2年は図工をしていました。
折った折り紙を切って、広げた時の幾何学模様の面白さに触れていました。
遊びの中での学びですね。



遊びの中での学びですね。



そして、20mシャトルラン!
息を切らしながら、自分の体力の力試しをしていました。みんな去年よりも記録が上がったことを喜んでいました。
達成感ですね。


達成感ですね。


遊び、そして学びの中の達成感は満足感になり、子供の自己肯定感を高めます。
遊びも夢中、学びも夢中、大人も子供も夢中になる時間を大事にしたいものですね。
サツマイモの苗植え
雨模様の中のサツマイモの苗植えとなってしまいました。
今日は、月立保育所の子供たちも一緒に苗植えをします。コロナ禍で出来なかった交流活動の再開にもなります。
まずは、お互いに朝のあいさつをしました。次に、今日、苗植えを教えてもらっている畑の先生とあいさつしました。




畑の先生からは、雨降りになってしまったけれど、実は苗植えには絶好の天気だと、気持ちが晴れるお話がありました。本当に優しい先生です。
苗の植え方で、サツマイモの形が変わることも教えてもらいました。「垂直植え」で植えると、丸いサツマイモとなり、「船底植え」で植えると長いサツマイモとなるとの事でした。分からない事って沢山あるものです。


さぁ、いよいよ苗植えです。長靴の底に土がくっついて、重さを感じながらバランスを崩さないように歩いていました。これも、大事な経験です。










月立保育所の子供たちも、小さな手で一生懸命に植えていました。



この苗植えにも、おうちの方々やこだま隊の方々にお手伝いをいただきました。小雨の中、本当にありがとうございました。
読み聞かせ&体力テスト
今朝は読み聞かせがありました。
読み聞かせボランティアの皆様は、子供たちに読み聞かせたい本を選んで当日を迎えているそうです。本当にありがたいと思っています。中学年の教室では、本に集まっている子供たちの姿もあり、心を揺らしながらの時間を過ごしていたのを感じていました。






そして、運動能力測定もありました。
全校で体育館に集まり、上体起こし=腹筋、立ち幅跳び、長座体前屈など、室内で行うことのできる運動をしました。








毎年の測定ですが、この「力試し」に少なからずも子供たちは関心があるらしく、わいわいしながら挑戦していました。以前にも書いた通り、自分との勝負ごとですので、負ける=思うように行かなかった…という気持ちにもなる場合も…。自分に意地を張らず、素直に気持ちと向き合いながら、小さくても、小さくても力強く一歩をふみ出す気持ちを育てられればと思います。
子供たちの力を信じて、応援して行きたいものですね☆ミ
梅雨入り
運動会、市内体育祭と、外での活動が一通り終えて、教室でしっとりと活動している姿がありました。この落ち着きが、新しい学びのスタートのように感じています。
2年生の算数の学習では、長さの学習をしていました。長さを表す「単位(たんい)」という言葉を覚え、その単位には「センチメートル(㎝)」があり、2㎝は1㎝何個分を学習していきます。その学習の中で、黒板用の1メートル物差しを見つけて、1㎝が何個あるのか「数えて」100個分だ!と言っていました。この「数える」という行為が、学びの中の「遊び」になるわけです。


遊びの主体は「子供自身」です。やらされているわけでは無く、自分から勉強している姿になります。次にやった遊びが、その物差しを使って「10㎝」を黒板に書いていました。この行為も学びの中の「遊び」で、主体は子供自身です。自分の遊びの中でやった行為は記憶に残ります。体験的活動と知識が結びついた瞬間です。月立小の子供たちは、なかなかいいセンスをもっていますね。


遊びの主体は「子供自身」です。やらされているわけでは無く、自分から勉強している姿になります。次にやった遊びが、その物差しを使って「10㎝」を黒板に書いていました。この行為も学びの中の「遊び」で、主体は子供自身です。自分の遊びの中でやった行為は記憶に残ります。体験的活動と知識が結びついた瞬間です。月立小の子供たちは、なかなかいいセンスをもっていますね。
高学年の教室では、野外活動のめあて作りをしていました。2つのグループそれぞれのメンバーが集まって、黒板に書いていました。


2つのグループに共通した言葉は「楽しく」です。この楽しさも、2年生の算数と同じように、自分から行動することで、楽しさを味わえます。そこに日々、導いているのが担任の先生であるは間違いありません。これから、どんな活動に楽しさがちりばめられているのか見守りたいと思います。


2つのグループに共通した言葉は「楽しく」です。この楽しさも、2年生の算数と同じように、自分から行動することで、楽しさを味わえます。そこに日々、導いているのが担任の先生であるは間違いありません。これから、どんな活動に楽しさがちりばめられているのか見守りたいと思います。
3年生は、風の力と車の進む距離の学習をしていました。理科の実験は、ほとんどの子供たちがワクワクします。


なぜなら、経験的に「風」と言うものを知っていて、その体験を基にした予想を立てやすいから、見通しがもちやすいのですね。廊下でサーキュレーターで風を起こし、その風の強さで進む距離がどうなるのか実験していました。あれ、2年生のセンチメートルの勉強が活用されていますね。そう思うと、毎日、これまで学習してきた内容を復習しながら今の学習をしていることになります。知らず知らずにですね。


なぜなら、経験的に「風」と言うものを知っていて、その体験を基にした予想を立てやすいから、見通しがもちやすいのですね。廊下でサーキュレーターで風を起こし、その風の強さで進む距離がどうなるのか実験していました。あれ、2年生のセンチメートルの勉強が活用されていますね。そう思うと、毎日、これまで学習してきた内容を復習しながら今の学習をしていることになります。知らず知らずにですね。
家庭での「お手伝い」「畑仕事」「花壇作り」「虫取り」、月立小学校での体験活動のすべてが、今後の子供たちの学習の支えになっていると思います。
最後に、今日はクラブ活動がありました。
4年生以上のみんなでドッジボールをしていました。先生方も参戦して、同級生には本気、下級生には思いやり、上級生には挑み、異学年でのドッジボールですが、上手く楽しんでいました。




4年生以上のみんなでドッジボールをしていました。先生方も参戦して、同級生には本気、下級生には思いやり、上級生には挑み、異学年でのドッジボールですが、上手く楽しんでいました。




子供たちの加減の付け方が上手で、この「加減」は異学年交流のたまものと思っていました。
先輩を敬い、後輩を思いやる、心の学びって、今しか出来ませんね。
先輩を敬い、後輩を思いやる、心の学びって、今しか出来ませんね。
学校の応援隊
4年生~6年生のかっこいい姿を思い浮かべながら、1年生~3年生は、外でお弁当を食べながら応援していました。


この先輩を思う気持ちが、後の自分が選手としてステージに立った時、「あの時、自分は学校で応援してたっけな…」という思いを馳せながら、「よし、がんばろう!」という気持ちを奮い立たせるより所になりますね。
誰かを思う気持ちは、必ず相手にもつながるし、未来の自分にもつながっているのですね。
とても大切な時間で、これからも大事にしたいですね。
体育祭
今朝は雨模様の中で学校に集合して、雷も鳴っていたことから開催が心配されました。
そんな中、ユニホームを着た選手が集まり、持ち物の確認の後、学校を出発しました。


会場では、ポツポツと雨粒が残る中、会場をランニングし、本番に備えます。
開会式での校名旗が集まる場面の確認もしていました。






30分遅れでの開会式が始まりました。月立小の代表11人の子供たちの凜とした姿は、学校を離れても同じでした。誇らしさを感じながら「よし!いいぞ!」と見ていました。そして、かけ声を掛けて、気持ちを一つにしました。少数精鋭の月立っ子の雄叫び!「オー」




競技が始まりました。テントから送り出す時、子供たちの緊張を感じながらも、精一杯自分の力を出すことを目標に、楽しんで来ることを伝え、それぞれ自分のステージに立っていました。



※写真がそろったら再upしますね。



※写真がそろったら再upしますね。
学校へ帰ってきた表情を見ると安堵感の表情で、ちょっとの心の成長があったものと思っています。




何よりも、自分のステージに立つ勇気はとても貴重な経験となります。成功もあれば失敗もあります。ただ、どちらも自分の中での「納得感」が大事で、その納得感に大人が寄り添うことが大切になります。
今日の景色を一緒に見ながら、次の景色のラフスケッチを一緒に描ければと思います。
頑張った後は、ゆっくり休む事も。
皆さんを誇りに思います。
皆さんを誇りに思います。
かっこ良く、すがすがしい姿、ありがとうございました。
壮行式
今朝は市内体育祭壮行式がありました。
参加する4年生以上が、月立小カラーの赤いユニホームを着ての壮行会です。
見ている方も、何だか気持ちが高まってしまいました。
体育主任の方から、選手の紹介があり、呼ばれた選手は手を挙げて返事をしていました。これは、本番でも同じですね。












選手代表のあいさつでは「練習の成果を発揮…」とい言葉もあり、練習してきたことの大切さを話していました。いつの時代も、自分との向き合いなのだと考えさせられます。




在校生代表では、3年生の2人が、エールの言葉を伝えました。「かっこういい姿…」という言葉もあり、上級生のかっこいい姿が、明日の選手を育てるのだと改めて思いました。
子供たちの緊張感をひしひしと感じ、その不安と向き合っている姿に対して、勝負事だから勝ち負けがあること。ただ、それ以上に自分の記録と向き合う事を伝えました。もちろん、そこには「…発揮出来なかった…」という思いも出てくるかも知れませんが、その事に触れた事に意味があるのだと思います。

明日1日は、丸ごと全部、大事な時間になると思っています。
今晩は、月立小の子供たちのために、みんなで「勝負めし」食べましょう(^_-)
明日は、みんなで応援!頑張ろう!
市内体育祭に向けて~本番仕様~
今週の水曜日の体育祭に向けて、本番仕様の練習をしました。
本番に向けての気持ちづくりをするためには、ほどよい緊張を感じさせながら、競技することの模擬練習が必要ですね。


















実際のスタート時の「バン」という音や、周りの声援を受けての走り、ゴールの瞬間などの調整が必要です。今日は、すべてを含めた時間となりました。
明日は、壮行会があります。
みんな緊張の中で、本番を迎えます。
フレー フレー 月小!!
遊び
天気が良い日は、みんなで校庭に遊びに行きます。
授業が終わって、昇降口から校庭に向かって走って行く姿は、子供らしくていいものです。


のぼり棒の逆上がりを一緒にしてみました。
逆上がりは、子供たちの中での「出来るようになりたい」と思う技のひとつです。今も昔も同じですね。日常の中で「逆さ」の感覚に触れることで、新しい動きをするためにきっかけができあがります。そこで、小さい学年は、ジャングルジムの中での逆さ遊びや、のぼり棒での逆さ上がりをすることで、一本の棒=鉄棒の中での逆上がりが完成します。
逆上がりは、子供たちの中での「出来るようになりたい」と思う技のひとつです。今も昔も同じですね。日常の中で「逆さ」の感覚に触れることで、新しい動きをするためにきっかけができあがります。そこで、小さい学年は、ジャングルジムの中での逆さ遊びや、のぼり棒での逆さ上がりをすることで、一本の棒=鉄棒の中での逆上がりが完成します。
遊びは伝承活動です。上級生が教えたり、おうちの方や先生方が教えないと遊びは広がりません。
そこは、バーチャルではなく、「リアル」です。
月立小学校は、自然が豊かで多くの「リアル」にふれることができる場所です。
大人も子供も、五感+αを研ぎ澄まして、リアルを楽しみましょう✨
朝の会
1・2年生の教室に行ってみると、朝の会をしていました。
日直さんが司会をして、1日のめあてを決めていました。




めあては「正しい姿勢にしよう」となりましたが、その時の理由が、よくある理由付けであると…「姿勢が良くない人がいるからです」となりがちですが、ここでの理由が「正しい姿勢で聞くと、話が良く聞けるからです」と発表し、「良い行為=みんながめざす姿」を理由にしていたところが、”すごい”と感じました。
このように導いているのは、担任の先生の日々の関わりであると感じています。
子供たちは、日々、様々な「良いこと」「悪いこと」に触れて成長しています。時には間違う事もあります。その時「○○がダメだから、やめましょう…」では、子供たちがめざす姿が見えにくいものです。そこは、「○○にするために、こんなことをしましょう…」の方が具体的な行動に結びつきやすいものです。
子供たちが、ぐーんと伸びるチャンスには、失敗や間違いもありますね。
温かく見守りましょう✨
引き渡し訓練
今日は新月中学校区の3校合同引き渡し訓練がありました。
地震が発生し、警報発令解除後の引き渡しの訓練で、学校と保護者の皆さんと、手順を共有する時間でした。
学校では、地震発生から校庭への避難、引き渡しという手順を子供たちと共有し、いざというときに、その手順を基にしながら、自分の命を守る判断力を養う時間でもありました。








想定外のリスクを小さくするためには、いつも想像力を働かせて、日常の災害報道を自分事としておく「クセ」をつけておくことが大事となりますね。それは、子供も大人も同じで、家族で報道をきっかけに、団らんの中で確認する事が、防災・減災の小さな一歩になるように思っています。
一人一人の頭の中の想像には限界はありません。その一人一人の想像を、様々な方と出し合い、共有する事でリスクが小さくなります。
子供たちを守り、自分を守り、そばにいる人を守る。
毎日の小さな一歩を大事にしたいものですね。
学校教育目標
ふるさとに誇りをもち
夢と希望に満ちた
心豊かでたくましい 児童の育成
目指す児童の姿
【き】 気持ちよくはたらく子
【だ】 だれにでもやさしい子
【て】 ていねいに学ぶ子
本校のいじめ防止対策基本方針
月立小学校 いじめ防止基本方針について掲載します。
GIGAスクール構想について
気仙沼市 GIGAスクール構想.pdf
気仙沼市 タブレット端末貸与について.pdf
